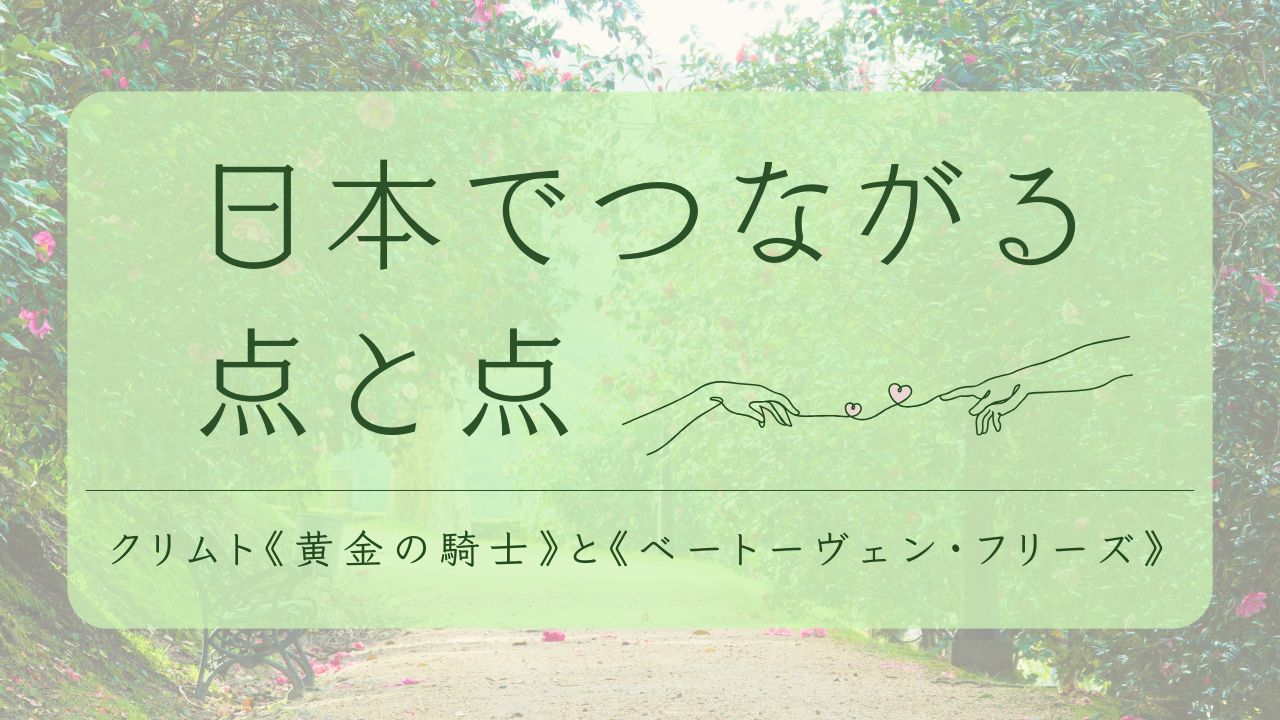クリムトの作品集を見ていたら…まさかの発見があったんです。
そこに描かれていたのは、黒い馬に乗った「黄金の騎士」。
クリムト《人生は戦いなり(黄金の騎士)》1903年、愛知県美術館蔵
解説を読み進めると、これは《ベートーヴェンフリーズ》の黄金の騎士を独立させた作品と書いてあり、さらに驚きました。
実は、この作品…過去に展覧会で出逢っていたんです!
その再会のきっかけを与えてくれたのがこちらの本↓
この作品が目に止まった時、あの時の体験と今がつながり…
まさに点と点が1本の線になったような瞬間でした。
新しい意味を帯びたあの日の記憶
一番胸が熱くなったのは、自分自身がこの《人生は戦いなり(黄金の騎士)》に再会したこと。
2022年、地元で開催された特別展にこの作品が来ていたんです。
当時、きらびやかで美しいと感じたのは確か。
ただ、今こうして調べ直してみると、それが《ベートーヴェン・フリーズ》から発展した作品であり、クリムトの芸術的闘争の象徴だったこと知って…
あの時の体験がまったく違う意味を帯びて立ち上がってきました。
さらにその展覧会ではクリムトだけでなく、エゴン・シーレの作品も展示されていて。
2人の空気を同じ空間で感じられたのも、忘れがたい経験でした。
「美しい装飾画家」と思っていたクリムトが、こんなに戦う精神を秘めていたなんて…
その気づきは、改めて胸に迫ってきました。
《黄金の騎士》とは?
1903年、第18回ウィーン分離派展に出品された作品。
題名が示す通り、「人生とは闘いそのもの」というメッセージが込められています。
黄金の鎧をまとった騎士は黒馬に乗り、左から迫るヘビ(悪や誘惑の象徴)と対峙します。
私は当時このヘビを探せず、会場を2周してようやくその姿を見つけました。
そのとき、ヘビの瞳に「誘惑におびき寄せられる」ような感覚を覚えたことを思い出しました。
背景は深い森、足元は黄金の地。
まるで中世の物語をそのまま絵にしたような幻想的な光景です。
《ベートーヴェン・フリーズ》とのつながり
この騎士の姿は、前年に描かれた《ベートーヴェン・フリーズ》の一部に由来します。
人類の願いを背負い、敵に立ち向かう「黄金の騎士」。
それをクリムトは発展させ、独立した油彩画として描いたのです。
フリーズでは剣を構え直立する姿でしたが、《人生は戦いなり(黄金の騎士)》では馬に乗り槍を持つ。
背景も「現実の戦い」から「夢の楽園」へと変わっています。
同じ騎士でも、舞台を変えることで、より内面的で精神的なメッセージへと深化しているように思います。
背景にあった「芸術の闘争」
この頃のクリムトは、ウィーン大学天井画事件で猛烈な批判を浴び、権威と決別した直後。
孤立と批判の渦中で描かれた《人生は戦いなり(黄金の騎士)》。
単なる英雄像ではなく、自らを重ねた闘う芸術家の姿でもありました。
最後の大規模なマニフェストとしての性格を持ち、クリムトの芸術観を凝縮した一作だったのです!
まとめと次回予告
クリムトの《人生は戦いなり(黄金の騎士)》は、中世風の装飾画に見えて、実は彼自身の闘争の象徴。
《ベートーヴェン・フリーズ》から発展し、大学天井画事件を経て生まれた、戦うクリムトの姿でした。
そしてわたしにとっても…
3年前には「金色のきらびやかな絵画」と思って眺めていたものが、今になって意味を持ってよみがえった特別な作品です。
次回は、この騎士からさらに広がって…
映画『グランド・ブダペスト・ホテル』に登場する退廃芸術のシーンを切り口に、歴史や時代の空気をたどってみたいと思います!
映画『グランド・ブダペスト・ホテル』はこちらからも観れますよ↓
▶︎Amazonプライムビデオで観てみる