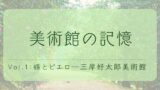見慣れないお菓子に書かれていた名前からはじまる旅
先日いただいたグミ。
見たことがないお菓子だったので、ほんの少し食べてみようと袋を開ける。
すると4種類の味があるはずなのに…出てくるのはパイナップル、パイナップル、またパイナップル。
さらに3つ連なって出てきたときには、思わず笑ってしまった。
マンゴー、ラズベリー、シトラスも探して食べてみる。
フルーティで、やわらかい食感。
「彩果の宝石」のような、フルーツのかたちをしたちょっと特別なジェリー。
しかもヴィーガン。
そんな中でパッケージを何気なく眺めていたら…
そこに書かれていたのは「ピエログルマン」という名前。

「ピエロ」と何か関係あるのだろうか?
「ピエログルマン」とピエロの歴史
気になって調べてみたところ、このグミを作っているのはフランス生まれのキャンディブランド「ピエログルマン(Pierrot Gourmand)」。
1892年に創業された老舗のお菓子屋さんだそう。
公式のホームページを見てみると、ブランドのシンボルとなったおしろいをまとったピエロの胸像、お菓子や果物を抱えたピエロ、お菓子の箱の中でおどけるピエロの姿が。
…このお店は、「ピエロの魂」をずっと受け継いでいるのかな?
ピエロはもともと、イタリアの仮面劇『コンメディア・デッラルテ』から生まれたキャラクター。
そして、19世紀のパリでは、ジャン・ガスパール・ドビューローという無言のパントマイム芸人によって、言葉を使わずに感情を伝える存在として再解釈されたのだそう。
「ピエログルマン」は、そんな哀愁と優しさをまとったピエロを、甘いひとときとして届けたかったのかもしれない。
モンマルトルに生まれた哀しきピエロ
さらに調べていくうちに、モンマルトル劇場文化とピエロの関係にたどりつく。
19世紀末のパリ。
キャバレーや舞台芸術が花開くなか、ピエロは「笑いの裏に哀しみを抱えたキャラクター」として独自の地位を築いたそう。
しゃべらず、泣かず、ただ静かに感情を漂わせる存在。
もはやただのピエロではなく、「孤独の象徴」のように見えてくる。
なぜピエロに惹かれたのか?
実はこのグミに出逢う少し前、わたしはヴァトーの《ピエロ》や三岸好太郎の《道化役者》という絵に心を奪われていた。
どちらもどこか哀しさをまとったピエロたち。
笑っているのに寂しげなあの瞳。
派手な衣装とは裏腹に、どこか孤独を抱えた切ないそのピエロの姿。
そんなタイミングで偶然手にしたこのグミ。
もうこれは、ピエロに呼ばれている?!
ヴァトーの《ピエロ》や三岸好太郎の《道化役者》についての記事は、こちら
お菓子は「記憶のとびら」なのかもしれない
名前も時代も違うピエロたちが、記憶の中で静かにつながっていくような感覚。
お菓子ひとつで、こんなふうに心の旅ができるなんて。
もしかしたら、わたしにとってのお菓子って「記憶のとびら」なのかも…
そんなことを考えていたら、ほんの少し味見するはずだったグミは気づけばパッケージの中から消えていた。
カルディに売っているようなので、見かけたら買ってしまいそう。
今度は冷やして食べてみたい!